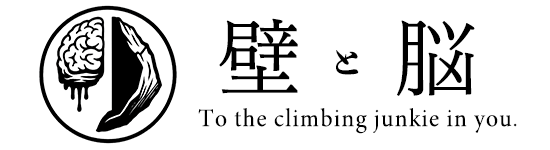第1話『岩を登らない奴はゴミ』
日常をこなしながら、頭の中は岩場のことばかり。
社会のルールに適応するふりをして、本当はすべてを嘲笑っていた。
そんなヤスが、ある金曜の夜、ひとりの少女と出会う。
29歳、神奈川の会社員
名ばかりの正社員、土日祝休み。
――ヤスは、ごく普通の肩書きを持っている。
平日は普通の顔をして会社に通い、
「いいっすね〜」と上司に合わせ、同僚とも普通に会話をする。
だが、その脳内の9割は、次の外岩のことで埋め尽くされていた。
ジムは、所詮はトレーニング場。
ヤスにとって、本番は「岩」だった。
岩に登っている時だけが、至福だ。
人工壁では、魂が震えない。
社会への違和感
上司が得意げに話す。
「最近さ〜、新車買ったんだよね!○○のSUV!」
「マジっすか〜!?いいなぁ〜!」
羨ましがるふりをしながら、ヤスは心の中で呆れ返っていた。
(へえ、立派な車だな。
でもどうせ週末はショッピングモールで、岩場に行かず悪路走行もしないだろ?
しかもこの手のオシャレSUVはマットも2、3枚しか積めない。
高いローン払ってこんな車買うなんてコイツ頭沸いてんのか?)
同僚たちも、滑稽だった。
週末になると口を揃えて言う。
「彼女とディズニー行くんだ!」
「ミラコスタ泊まるんだよね〜」
ヤスは、内心で鼻で笑っていた。
ディズニーランド。
クライミングを始める前、当時の彼女や友人と何度か行った事がある。
当時、それが幸せで楽しいと感じていた自分が信じられない。
魔法の国。夢の時間。
そんなものに金払って並ぶような人生、今は心底軽蔑している。
お前らは、
着ぐるみを着た鼠に愛想笑いされるために働いているのか。
ネズミの顔したクソ高いピザを食うために人生を切り売りしているのか?
「ネズミに夢見てる暇があるなら、岩に指突っ込んで血流してろ。」
ヤスにとって、クライミングだけが現実(リアル)だった。
そこには、ファンタジーなんて一切ない。
たとえ登れなくても、指が裂けても、マットに叩きつけられても、
それは間違いなく「本物」だった。
そんな「本物」も知らずに
ディズニーのミッキーに手を振っている連中――
心底、虫唾が走った。
無害な仮面と冷たい火
表向き、ヤスは優しい。
無害そうに振る舞う。
だが、その胸の内には、冷たい火がずっと燃えていた。
「岩を登らない奴ら」と「岩登る自分」。
その境界線は、年々、深く、冷たくなっていた。
最近はマリッジブルーだの、ウェディングフォトだの、
他人の幸福アピールが洪水みたいに押し寄せてくる。
(わざわざ写真を投稿しないと証明できない愛って、哀れだな。)
そんな毒を内に抱えながら、ヤスは帰りの電車に乗る。
吊革に掴まる隣のリーマンは腹がはみ出していた。
ビール腹。デスクワークの象徴。
ベルトに腹が食い込んで、シャツが引きつれている。
(生きてるっていうより、腐って膨らんでるだけじゃねえか。)
心の中で吐き捨て、スマホを開く。
自分のインスタ。
外岩完登の写真たち。
真剣な表情でホールドを握る自分。
(……これが、俺の”リアル”だ。)
だけど、いいねの数はそこまで伸びない。
40件。50件。
かすかな承認だけが、小さく点灯している。
ほんの小さな救い
そんな日々でも、ヤスには救いがあった。
ホームジム。
ここだけは違った。
誰も「どこ大卒か」とか「年収いくら」とか聞かない。
ただ、壁と、指と、フリクションだけがすべてだった。
ジム仲間のマツヤマさんも、渡辺さんも、タケも。
誰一人マウントを取らない。
完登したら「ナイス」とグータッチ。
失敗しても「ナイストライ」の言葉。
(……この空気だよな。
まともな人間は、ここにしかいない。)
ヤスはそう信じていた。
金曜の夜に
金曜の夜、
翌日の外岩に備えて軽く登ろうとジムへ向かった。
そして、そこで出会った。
明るい色のTシャツ。派手なレギンス。レンタルシューズ。
ぎこちない手つきでチョークをまさぐる女。
――ミキ。
ヤスは興味なさげにスルーしかけた。
けれど、耳に届いた小さな声に、思わず足を止める。
「私……もっと、登れるようになりたいんです。」
ヤスは、一瞬だけ、目を細めた。
(……珍しいな。)
その瞬間、
彼の中で、何かが微かに動き出していた。
第二話へ(続く)